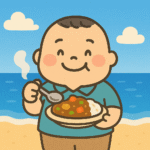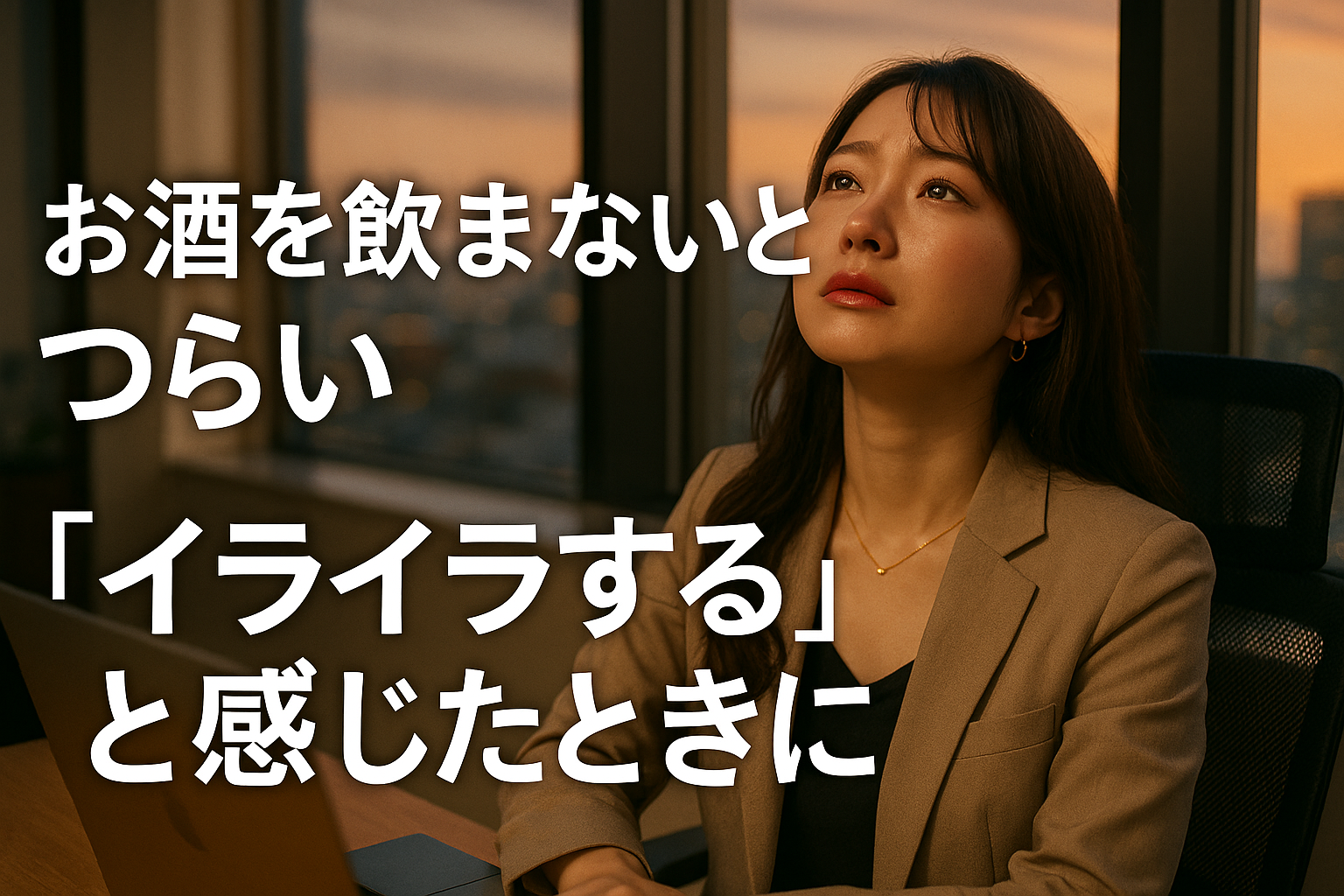「お酒は二十歳から」は注意喚起ではなく宣伝だった|断酒して見えた刷り込みの正体
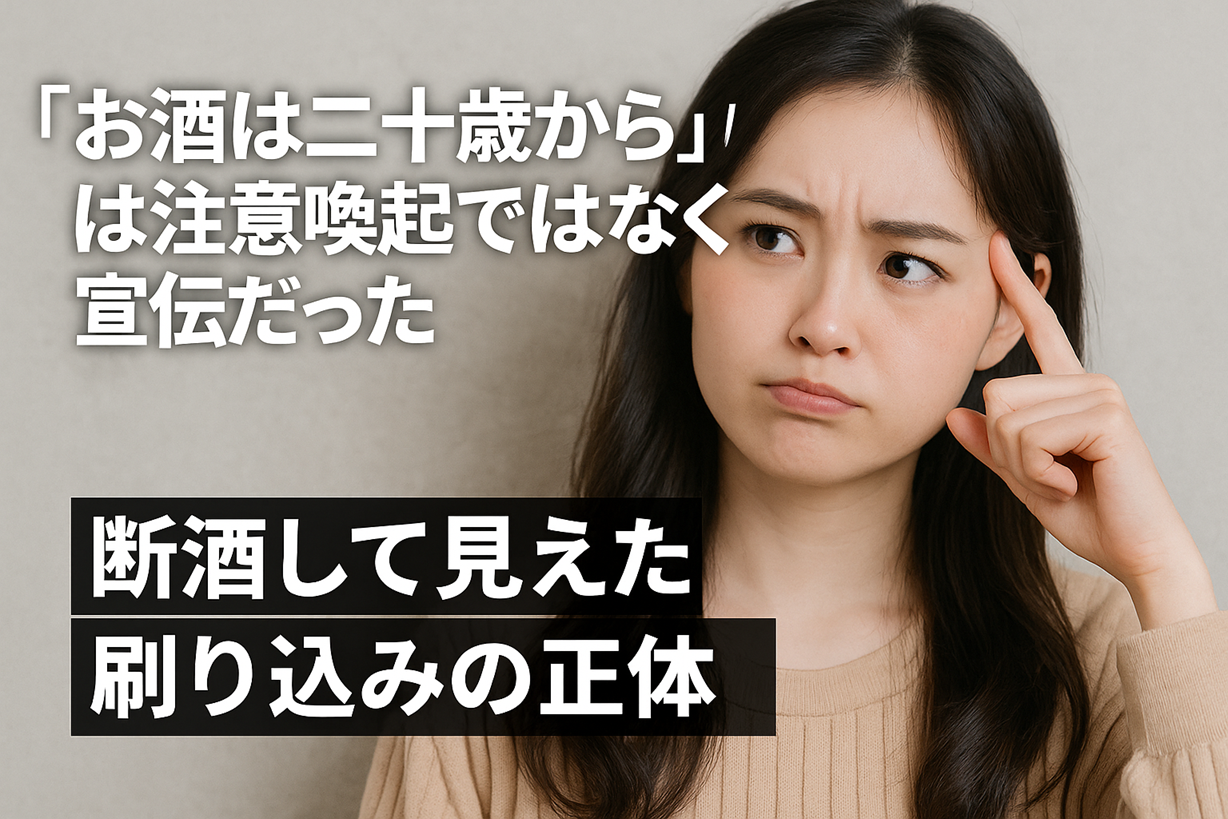
「お酒は二十歳から」。
子どもの頃から繰り返し聞かされ、まるで法律の決まり文句のように浸透しているフレーズ。多くの人は「未成年は飲んではいけない」という注意喚起だと思ってきたはずです。
しかし実は、これは国が定めたスローガンではなく、酒造業界による宣伝コピーでした。
つまり「注意」ではなく「飲むための入口」へと誘う“刷り込み”だったのです。
僕自身、断酒を始めてから初めてこの事実に気づきました。
そして気づけば気づくほど、どれだけ多くの場面で「お酒を飲むのが当たり前」と思い込まされてきたかを実感します。
この記事では、
- 「お酒は二十歳から」の正体
- 幼い頃から体に刻まれてきた酒の刷り込み
- 幻想に気づくことで見える飲酒の無意味さ
について、断酒経験者の視点からお伝えします。
「お酒は二十歳から」はどこから始まったのか
実はこのフレーズ、法律に書かれているわけではありません。
発信源は酒造業界のキャンペーン
- 1980年代、日本酒造組合中央会など酒造業界の団体が若者向けに広めたコピー。
- 表向きは「未成年飲酒を防ぐため」とされていたが、実際は「20歳を過ぎたら楽しくお酒を飲みましょう」という前向きなメッセージ。
つまりこれは「国からの禁止事項」ではなく「業界の宣伝戦略」だったのです。
注意喚起に見せかけた“歓迎メッセージ”
表面的には「20歳未満は禁止」。
しかし裏を返せば、「20歳になったら堂々と飲んでいいんだよ」という“歓迎メッセージ”として機能しました。
- 成人=お酒デビュー
- お酒は大人の証
- 飲むのが当たり前
こうした文化を、僕たちは子どもの頃から無意識に刷り込まれてきたのです。
断酒して気づいた「刷り込み」
お酒をやめてから、あらためて気づきました。
僕たちは「飲むかどうかは自分で選ぶ自由がある」はずなのに、社会全体が「大人になったら飲むのが普通」と決めつけていたんです。
飲酒を前提とした思考の罠
- 飲み会に行けば当然飲むもの。
- 酒を飲めないと「つまらない人」と思われる。
- 成人式や就職、結婚など、節目にはお酒がつきまとう。
これはすべて「お酒は二十歳から」というコピーが後押ししてきた価値観です。
他にもある「酒の刷り込み」
① 幼い頃から見てきた“大人の酒”
僕たちは、幼い時からことあるごとに、大人が酒を飲んでいる姿を見てきました。
冠婚葬祭などの嬉しいときや悲しいとき──どのような場面でも、お酒は大人のそばにありました。
その光景が繰り返し刷り込まれていくことで、
「大人になったら自然に飲むもの」
という無意識の前提が作られていったのです。
② 疲れたときに飲めば疲れが取れるという幻想
仕事で疲れたとき、「とりあえず一杯」という言葉があります。
でも実際には、アルコールは疲労回復に役立つどころか、体の回復を妨げます。
一瞬ラクになった気がするのは、単なる脳の錯覚。
翌朝のだるさや自己嫌悪を考えれば、「疲れを取るどころか、疲れを増やしている」のが現実です。
僕の体験:断酒して初めて見えたこと
断酒を始めて100日を超えたあたりで、この言葉をふと思い出しました。
「お酒は二十歳から」と言われてきたけど、本当は「お酒を飲まない自由」だってあるじゃないか、と。
子どもの頃から植え付けられてきた刷り込みに気づくと、逆に「飲まない選択の自由」がとても軽やかに感じられるようになりました。
そして今では、こう断言できます。
刷り込みに気づくことで、飲酒の無意味さがはっきりと見えてくる。
断酒目線でのまとめ
「お酒は二十歳から」は、注意喚起に見せかけた宣伝コピー。
僕たちは無意識に「飲むのが普通」という前提を刷り込まれてきました。
でも断酒を選んだ今は、こう思います。
- 「お酒はゼロでも生きられる」
- 「飲まない自分を選んでもいい」
- 「宣伝に乗せられなくてもいい」
まとめ
「お酒は二十歳から」。
これは単なる注意喚起ではなく、飲酒を当たり前とする文化を広めるための“刷り込み”でした。
そして僕たちはそのほかにも、
- 幼い頃から見てきた大人の酒の姿
- 疲れに効くという幻想
といった刷り込みを受けてきました。
でも断酒を始めて改めて気づきます。
刷り込みを疑うことで、飲酒の無意味さがはっきりと見えてくる。
そして「飲まなくてもいい自分」を選べる自由が、僕らの手の中にあるのです。