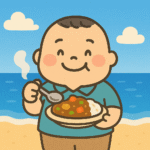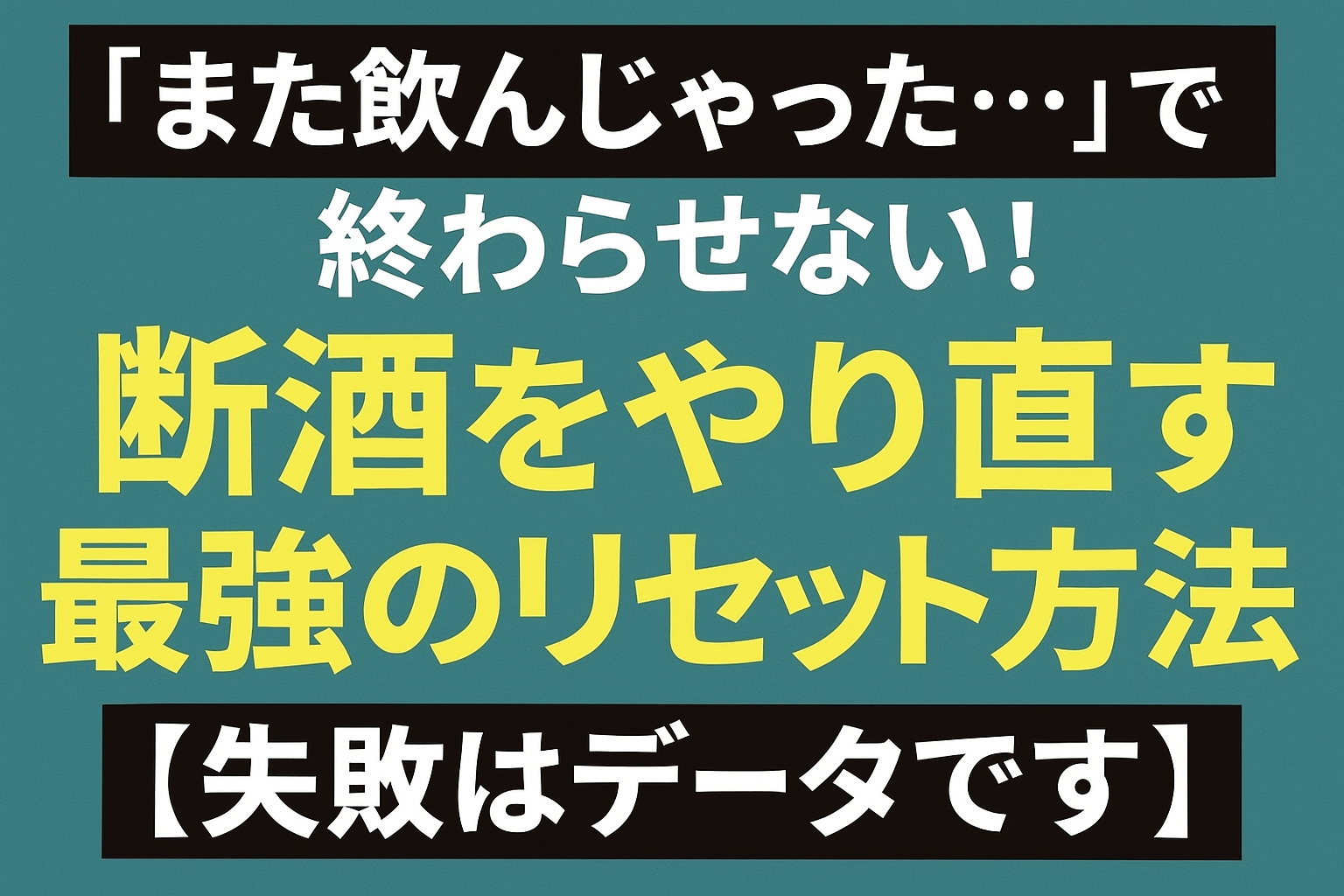気持ちがくさくさする時、酒じゃなくても乗り越えられる。断酒中の“やり過ごし方”実践ガイド
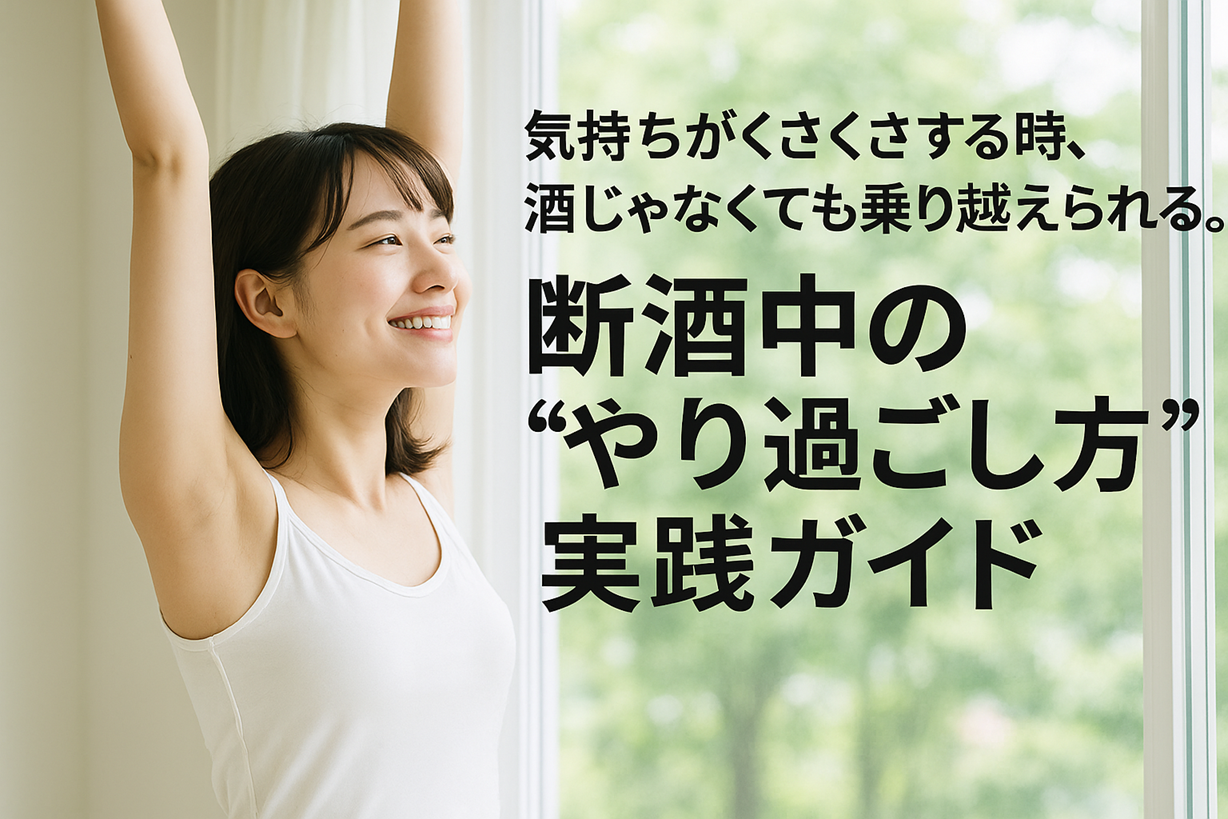
気持ちがくさくさしてどうしようもない時、昔の僕なら迷わず酒に手を伸ばしていましたが、今では「酒を飲んでも解決しないどころか翌日の自己嫌悪や不調を招くだけ」とわかっているので、酒に頼らず過ごす方法を探しています。
この記事では、そんな断酒中に訪れるイライラやモヤモヤの正体を整理し、科学的な根拠に基づいた対処法と、実際に僕が試している“飲まずにやり過ごす”具体策をお伝えします。
1.くさくさした気分の正体とメカニズム
「くさくさする」という言葉の裏側には、ストレス・疲労・将来不安・孤独感など複数の感情が混ざり合っています。
脳科学的には、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質のバランスが崩れると、気分の乱れが強く出やすいことが知られています。
アルコールは一時的に脳内物質を刺激して気分を変えますが、反動としてさらに落ち込みを強める作用もあるのです。
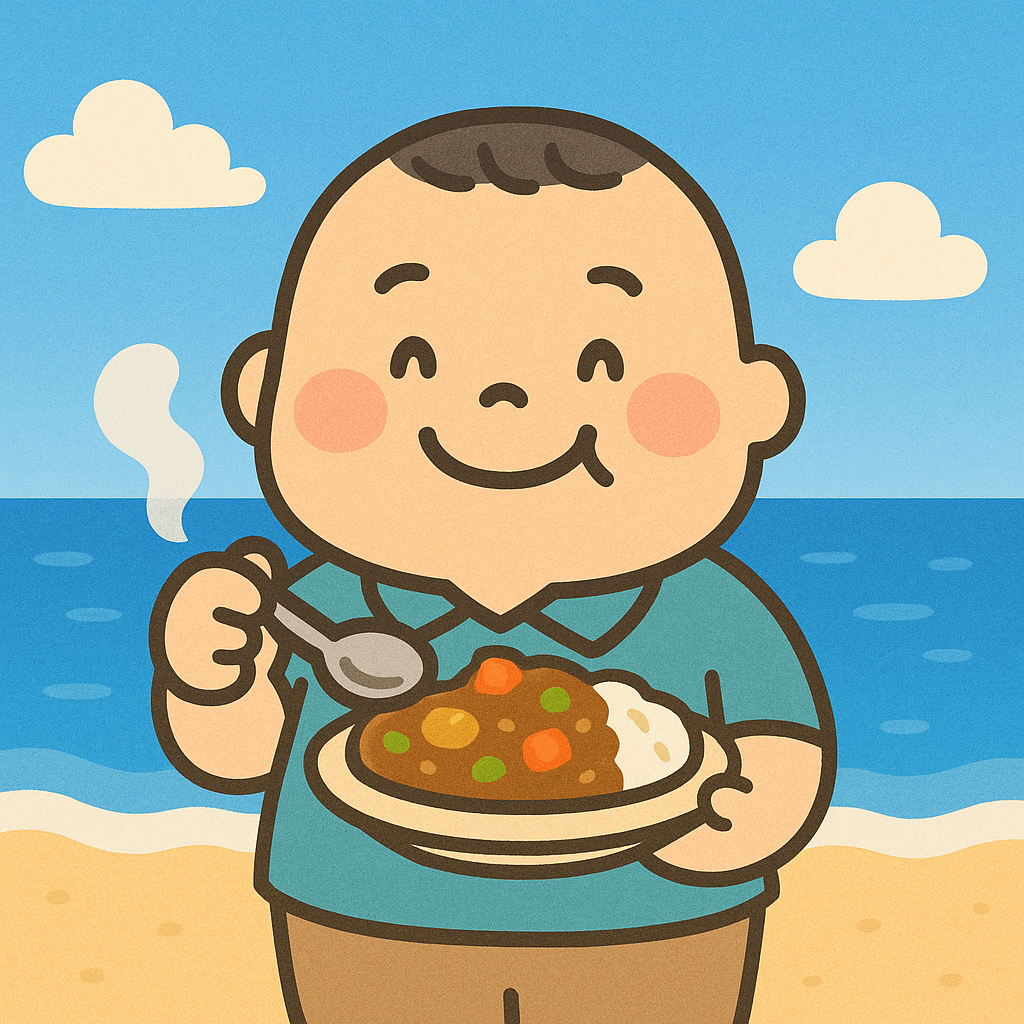
“くさくさ”って実は感情のバグ。放っておくと酒につながるから、正体を知るだけでも対処しやすくなるんだよね。
2.酒に頼ると悪化する理由と悪循環の構造
「飲めば気が晴れる」という思い込みは強力ですが、実際には悪循環の入り口です。アルコールは入眠を早める一方で、深い眠りや夢の眠りを乱し、夜中に何度も目が覚める原因になります。その結果、翌朝の疲労感が強まり、気分の落ち込みが増幅されるのです。
さらに、飲酒による血糖値の乱高下や、翌日の脱水・頭痛・胃の不快感が「二日酔い」という形で現れます。これが「昨日のストレスを酒で解消したはずなのに、なぜか今日も気分が悪い」というループを生み出します。
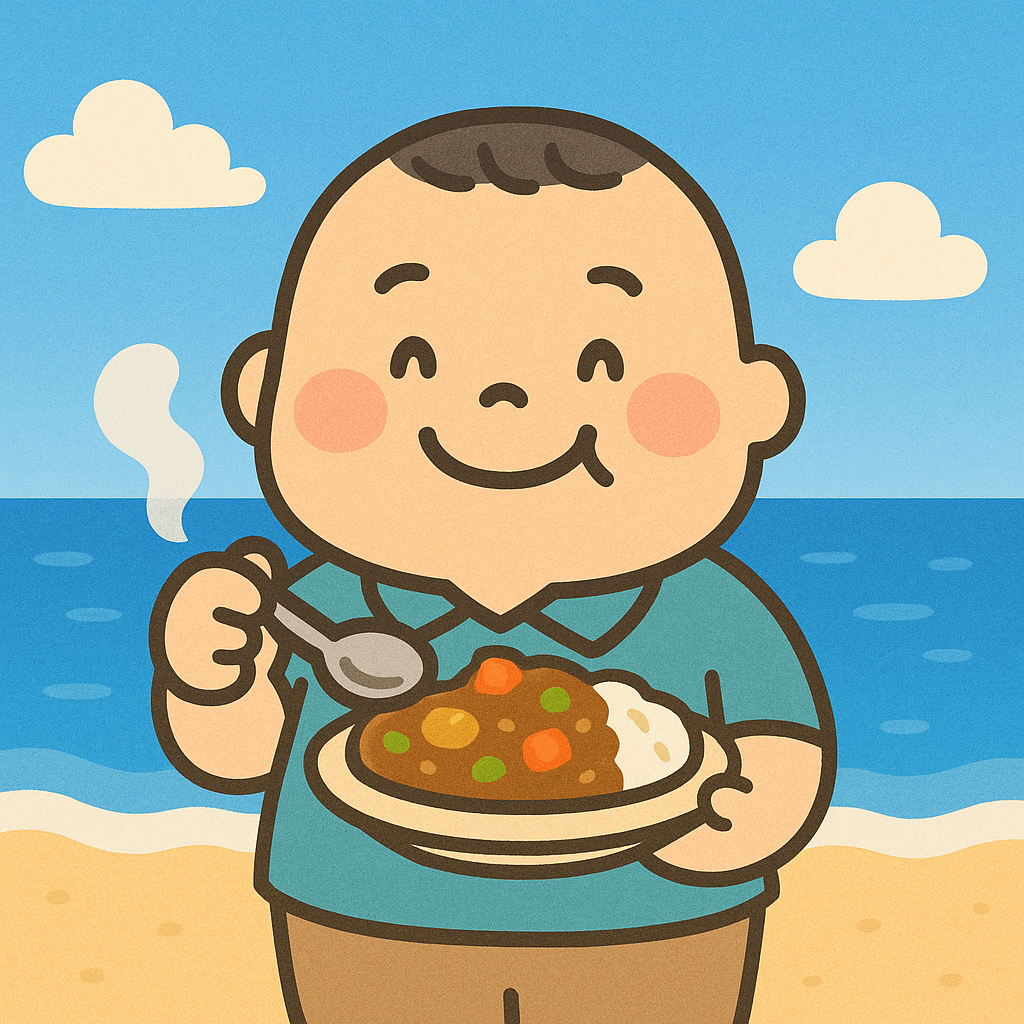
酒で一瞬ラクになるのは、床下にゴミを押し込むのと同じ。翌日になって倍返しで戻ってくるから怖い。
関連記事▶ 飲酒のメリットは本当にあるのか?“飲む理由”の正体とは
3.飲まずにやり過ごすための具体策と実践例
断酒を続けるためには、「代わりに何をするか」がとても重要です。ここでは、科学的エビデンスがある方法と、僕自身が実践して効果を感じた方法を組み合わせて紹介します。
3-1.体を動かす
散歩やストレッチなど軽い運動でも、不安や落ち込みを和らげる効果があります。僕自身、10分海沿いを歩くだけで「まあ飲まなくてもいいか」と気持ちが切り替わります。
3-2.ノートに書き出す
紙に気分を書き出す「表出ライティング」は、ストレスを軽くする効果があるとされています。頭の中の渦を外に出すだけで心がスッと軽くなります。
3-3.環境を変える
部屋の片づけやカフェへの移動、湯船に入るといった小さな行動で感情をリセットできます。
3-4.小さな快楽で置き換える
ノンアル飲料や音楽を“ご褒美”にすることで「飲む行為」を別習慣に切り替えられます。
3-5.未来に投資する行動
ブログを書く、資格の勉強をするなどの「未来に残る行動」を選ぶと、翌朝の自己肯定感が大きく変わります。
関連記事▶ 断酒で変わる朝のルーティン|50代から始める“整う習慣”
4.睡眠を守ることが最大の防御策
飲酒による「寝落ち」は一見ラクですが、翌日の集中力や気分を台無しにします。
逆に、湯船・ノンアル・早寝のシンプルなルーティンを徹底するだけで睡眠の質は改善されます。睡眠が整えば、気分の乱れも自然と落ち着き、飲酒欲求も弱まっていきます。
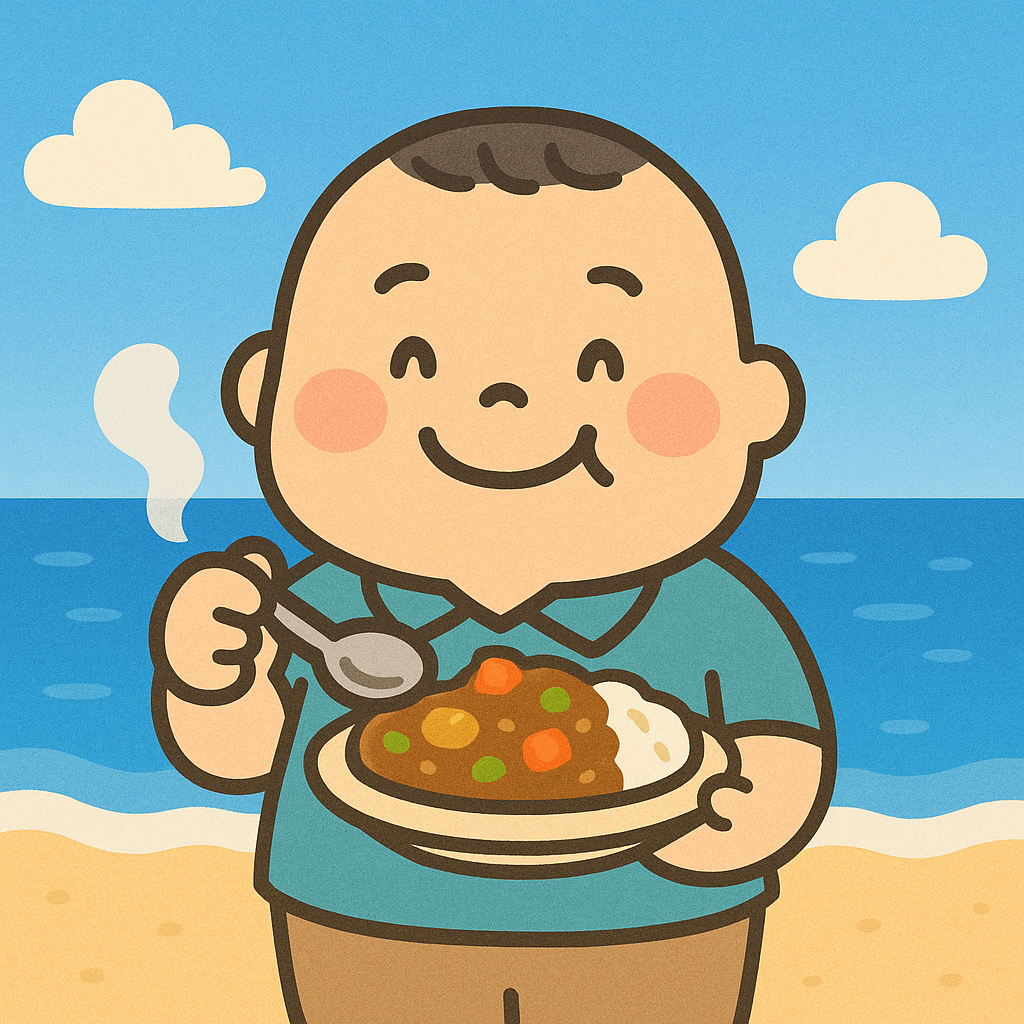
飲んで寝落ちは最短ルートに見えて、翌日を台無しにする最長ルートだったんだよね。
関連記事▶ 寝るだけで痩せる?ダイエット成功のカギは“睡眠時間”だった
5.その夜を切り抜ける“5分プロトコル”
僕が実際に使っている「5分で気持ちを切り替える方法」は次のとおりです。
- 2分片づけ:机とシンクを整える。
- 1分呼吸:4秒吸って6秒吐く呼吸を5回。
- 1分記録:気分を数値化し、一言メモを書く。
- 1分宣言:「今日は飲まない。その代わりに◯◯する」と声に出す。
関連記事▶ 飲み続ける限り金は残らない|酒代の闇と断酒の気づき
6.まとめ──翌朝の自分に「よくやった」と言うために
気持ちがくさくさする夜は誰にでも訪れます。大事なのは、酒ではなく“別ルート”を選ぶこと。
運動・書く・環境を変える・睡眠を整える──この積み重ねが翌朝の自己肯定感につながります。そして「昨日の自分、よくやった」と言える朝が増えていくこと、それ自体が断酒の最大の報酬です。
関連記事▶ 飲酒の楽しさより、後悔しない安心を選ぶようになった理由
この記事の内容を、YouTubeで二人の掛け合い形式にまとめています。
耳だけで理解できるので、通勤や家事の合間にもぴったりです。